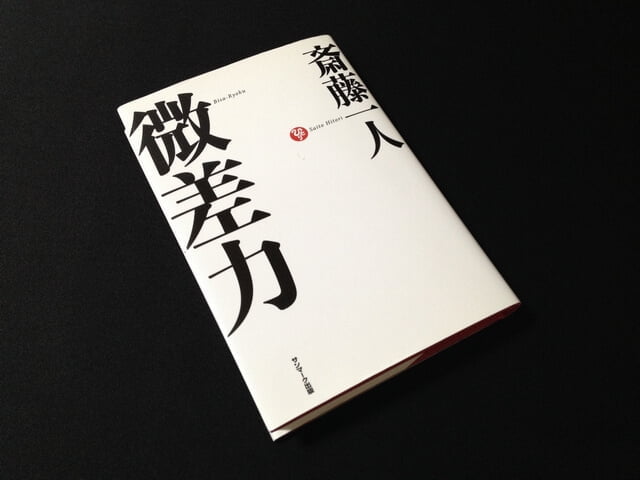タイトルから、ついつい「具体的なテクニックを教えてくれるのでは?」と期待してしまいがちですが、内容自体(特に前半部分)はむしろ自己啓発の比重が大きいです。
で、中盤から後半にかけて「こうすれば他と差別化できるよ」的なヒントがポツポツと出てくる感じでしょうか・・・テクニックではないかも。
また、筆者『斎藤一人』さんのクセ強めなワードセンスが邪魔してか、人によっては「入ってこないわぁ・・・」と感じられる場合があるかもしれません。自分のことを【さん】付けしたり、【天国言葉】などの宗教くさい造語だったり。
なので正直、文体としてはあまり私の趣味ではなかったりします。ただ、書かれていること自体は非常に説得力がありますし、とても参考になりました。
個人的に感銘を受けた箇所
脚立を持って富士山に登る
たとえば、たとえばの話ですよ。
日本一高い山といえば、富士山ですよね。
自分を日本で一番高いところに置きたかったら、富士山に登ればいいんですよね。富士山のてっぺんに行くと、日本で一番になれる。
ただ、富士山には、年間何万人かが登るんです。じゃあ、日本一になれないじゃないかと思うかもしれないけれど、ほとんどの人は、肝心なことを忘れているんです。それは何か。
富士山に脚立を持って行く人が一人もいない(笑)。
踏み台をかついで行って、山頂で踏み台を出して乗れば、日本史上最高に高いところに立てるのです。
せこい話かもしれないけど、事実上、そうなんですよ。脚立を持って行く。この微差で、大差なんです。
『微差力』82~83ページより引用
富士山を登るところまでは(センス・能力の差は多少あれど)横並びの状態。斎藤さんは富士登山で例えていらっしゃいますが、つまりはこれが "基礎" の部分だと言えます。
登山はやったことがないので分かりませんが、テレビの登山企画などを見ていると、念入りにトレーニングを行っていたりしますよね。高地順応トレーニングとか。
このトレーニングの段階で自分勝手にアレンジを加えると、最悪の場合、命を落としてしまうかもしれない。よって、この段階で他との差別化を考えるわけにはいかないわけです。
そして、基礎となる富士登山に成功したところで、ようやく "遊び" を取り入れてみる。本書ではそれを "脚立" で例えています。
盤石な土台の上に設置した脚立は、簡単には倒れない。その段階になって取り入れた "遊び" は安定感があるし、変化球的なことをやってもファンが付いてきてくれる可能性は高い・・・みたいなことなのかな、と。
"専門家にしかわからない" 微差と "素人が無意識に選ぶ" 微差
技術でいったら、βマックスのほうが上だったのです。だけど、VHSが軽いということは部品が少ない。部品が少ないということは安くできるんですよ。
いくら「βマックスの技術のほうが上だ」と言っても、映りは微差なんです。同じぐらいの映り、それが微差だとしたら、お客さんは安いほうを選ぶのです。
「微差でいいほう、いいほう」と言っても、その微差は技術屋にしかわからない。そうすると、値段が高ければ、安いほうを買っちゃうという。
こういうことを、デッキを持った瞬間、パッとわかっちゃう。
これが商売のカンです。
常に、微差を磨いている人に出てくる直感なんですよ。
『微差力』105ページより引用
『VHS』対『βマックス』と似たような対立構造として、『ゲームボーイ』対『ゲームギア』との関係も割と有名ですね。
単3電池4本で約35時間遊べ、外で画面が見やすく、値段が安いゲームボーイ。
単3電池6本で約3~4時間遊べ、外だと画面が見にくく、値段が高いゲームギア。
普通に考えたら、カラー液晶を搭載したゲームギアのほうが子ども達には喜ばれそうなものですが、任天堂はスペックよりも駆動時間を優先。その結果、全世界で約1億2千万台も売り上げるモンスター携帯ゲーム機へと成長しました。
市場を掌握した VHSとゲームボーイに共通しているのは、製品スペックと消費者の願望との "妥協点" を上手く見極めたことにあると思います。
スペックも大事ですが、多くの方々がもっとも目を引かれるのは結局 "コスパ" だったりしますよね。スペックを念入りに調べるようなヘビーユーザーの人口は、詳しくない方々に比べると圧倒的に少ないですし。
重続は力なり
車でループ橋を走っていると思ってもらうと、わかりやすいんですけれど。私はとりあえずやってみる。そして、ぐるーっと走って、一周してきたときには上にいます。わかりますか?
要は、最初の失敗の上に乗っかるんです。
そして、また、ぐるーっと回って行って、次、次って重なりながら、上にあがって行く。これをやっていると、競争がいらないのです。
だから、とりあえず、やってみる。やってみたら、「ここがマズかった、今度はこうしよう」とか、やってみてわかることがあるのです。
そうすると、それを改良して、またそこへ来て改良して、また来て改良して・・・・・・という。これが神の仕組みなんです。
ぐるーっと回って、重続しながら上にあがるのです。
飛行機が離陸するときみたいに、直線状にあがるのではないのです。
『微差力』131ページより引用
『VR』なんかが、まさにコレですよね。
赤青セロファンの3Dメガネは大昔からあったし、2Dのヘッドマウントディスプレイなども昔から存在した。でも、技術力だったりコストの面で、高精細な3D空間はなかなか実現できなかった。でも近年になって VRが急激に注目され始め、割と本格的な3D空間を構築できるVR機器が "割と現実的な価格帯で" 手に入れられるようになりました。
これもひとえに、水面下で研究を "重続" していた技術者の方々による、血の滲むような努力の成果だと言えるでしょう。
ぶっちゃけ、言っていること自体は『PDCAサイクル』と一緒なのですが、日本語で表現されていると不思議と頭に入ってきますね。「継続ではなく、重続(重ねて続ける)なのだ」と。
ダラダラと日々のルーチンワークをこなすのではなく、改善点を見つけて、螺旋状に上へ上へと登っていく。一周して毎回同じところに戻ってきているように見えるんだけど、自分自身のスキルや知識が増えているから、以前できなかったことがスラスラとできるようになっていたりするわけです。
私は要領が良いほうではないのですが、それでもこの "重続" の効果を実感する場面は結構あります。仕事部屋の環境は徐々に良くなっているし、体力面・精神面も改善されてきているし・・・日々の積み重ねって大事です。
あとがき
実を言うと他にも、良いコトは山ほど書かれています。
本当はそれらもご紹介したいところなのですが、今回は本書のタイトルである『微差力』に該当する項目のみを厳選してみました。
というのが1つと、あとは・・・もう1冊、斎藤さんの著書をご紹介する予定があるんですね。で、もしかすると内容的に重複する箇所が出てくるかもしれないので、今回はこのぐらいにしておきます。
あと最後に。
テクニックうんぬんも大事ですが、本書が示唆しているのは、むしろ "急がば回れ" の精神ではないかと思います。
例えば「ライバルをきちんとリサーチしよう」「清潔感のある恰好をしよう」「自然な笑顔をつくろう」だとか。普段からやられている方にとっては朝飯前かもしれませんが、これから習慣として取り入れるとなると結構大変かもしれませんね。
つまりは「差別化したいんだったら、まず基本をやってからにしましょう」という話です。耳が痛い・・・
最新情報をお届けします